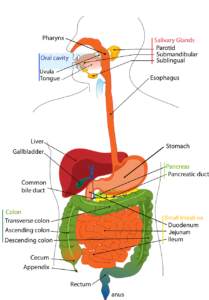日本語や文語が大切だという話題も、少し軽い内容から入ってみたいと思います。徳永文一『国際人には文語が似合う』(長風舎、2015年)には、思わず苦笑いしてしまう事例が出ています。
銀行に電話をしたとき、「○○さんいらっしゃいますか」と尋ねると、「○○部長さんはお席にいらっしゃいません」との返答。さらに別の電話では、「○○さんは、留守の形になっておりますので、おかけなおしでよろしいでしょうか」と返ってきたことがあるそうです。怒り心頭、「留守の形ってどういう形ですか、居留守をつかっていらっしゃるのですか」と、つい口をついて出てしまったそうです。それでも相手は、「いえ、そういう形になっております」というばかり。比較的しっかりした研修制度がある銀行ですら、このような状況なので、日本人の一般的な日本語運用能力は、相当低下しているものと思われます。
たしかに、言語は生きているので、新しい表現や言い回しは、時間の経過とともに増えていき、変異というものもあることでしょう。それは、文語文から口語文への流れをみていくと顕著に現れてきます。
古田島洋介『日本近代史を学ぶための文語文入門』(吉川弘文館、2013年)は若干難しい内容ですが、それでも一読の価値がある書籍です。そこには、文語文の一種である漢文訓読体について解説されています。漢文訓読体とは、漢文を明治の普通文にしたものといっていいかもしれません。明治普通文を翻訳すれば漢文になり、漢文を翻訳すれば明治普通文、すなわち漢文訓読体になるということです。専門家ではないので、正確な説明というよりも、わかりやすく、イメージしやすい説明ということでご了承ください。
そして、漢文訓読体は、句読点が付けてあっても、実は句点がなく、読点だけで切ってあることが珍しくないといいます。かつての日本語は、句点と読点の使い分けがなかったからだそうです。そのような場合は、自分で適宜に読点を句点に変えていく作業が必要になります。読点については、今日の日本語にさえ明確な基準はありません。その点、読み手、あるいは書き手に任されているということになります。
また、今日の日本語の文章は、改行すれば行頭に一字分の空格を設け、文は適宜に読点で切り、文末には句点を打つのが体裁上の約束事ですが、明治期の文章は、行頭を一マス空けることなく、句読点を一つも打たずに記してあることも多く、漢文訓読体も例外ではないそうです。体裁は一般にめりはりを欠き、改行が明らかでない点では、ベタ書きの印象を与え、句読点がいない点では、だらだら書きの雰囲気が漂います。学生時代に、民法学の名著、柚木馨『売主の瑕疵担保責任の研究』(有斐閣、1978年)読んだとき、改行がなく長々と続く文章に違和感を覚えたことがありましたが、おそらく大正14年生まれの柚木氏は、漢文訓読体の影響を引きずっていたのだろうと今わかりました。
このように、文語文から口語文への変遷を考えると、読みやすさを追及して、言葉はますます進化していることがわかります。ただ、進化させるとしても、基本と伝統を踏まえた上ででないと、前述のように乱れた日本語が横行してしまい、それこそ日本語の消滅を早めてしまいます。今、日本語を軽視し、英語を重視する風潮がみられますが、ここは立ち止まって考える必要があるのではないでしょうか。山口仲美『日本語が消滅する』(幻冬舎新書、2023年)で引用されていたある詩は次のとおり私たちに警告します。
「死にゆく言葉はそっと崩れ落ちる
あの村でもこの村でも
静かに倒れていく - 叫ぶこともなく
泣きわめくこともない
さらりと、ふいにいなくなる
鋭い目を持たなければ
その静かな破滅に気づかない
そしてつつましく、決意に満ちた心がなければ
それを止めることはできない」
鋭い目を持って日本語の行く末を見つめていきたいと思います。