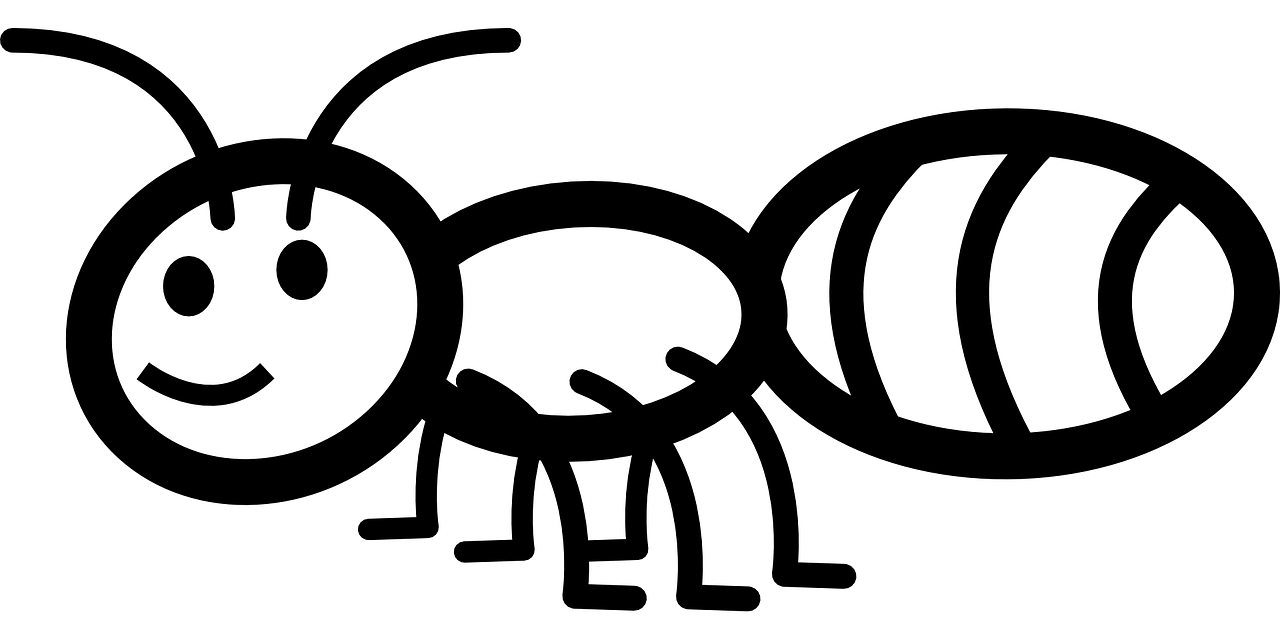
イソップ童話の「アリとキリギリス」は誰でもご存じだと思います。アリは働き者の典型として登場します。しかし、アリの生態を研究している北海道大学の長谷川英祐准教授による、多くのアリは働き者ではないといいます。
長谷川氏の著書『働かないアリに意義がある』(中経の文庫、2016年)によると、アリの巣の中の7割ほどのアリが何もしていないことがわかったそうです。そして、この働かないで何もしていないアリの中には、生まれてから死ぬまで働かないアリもいるということです。しかし、その働かないアリにも存在意義があり、働いているアリが疲れて働けなくなると、その働いていなかったアリが巣の存続のために働きだすそうです。
しかも、みんな同じようにみえるアリにも、それぞれ体に個性があり、標準的なアリばかりということではありません。規格品ばかりではなく、規格外のアリを集団に抱え込み、あえて非効率な状況を維持しているようなのです。しかし、それを非効率といってしまうのは浅薄であり、実はアリが達成した進化の形だといいます。
たとえば、一匹のアリが大きなエサをみつけて、そのエサを運ぶために他の仲間を呼び寄せるときに、フェロモンという匂い物質を地面につけて他のアリを導きます。賢いアリは、そのフェロモンの通り行動して行列を作るわけですが、たまに賢くないアリがいて異なる動きをすることがあります。そして、バカな行動をと思いきや、実はフェロモンの通りの道のりよりも、その賢くないアリがエサまでの最短のコースをみつけることがあるそうです。組織にはぐれ者がいるほうが実は効率的なこともあるという実例ではないでしょうか。
余裕を失った組織がどのような結末に至るかは自明だと長谷川氏はいいます。大学という組織でも、「役に立つ研究を!」というかけ声が高くなっています。しかし、何が役に立つかなど、その時点でわかるわけがありません。何の役にも立たないと思われている研究が、将来大いに役立つということはあります。
同じことは社会や組織についてもいえると思います。社会や組織に役立たない人材などいないのでしょう。たとえば、一見、役に立たない人材と思われている人にも、組織に微妙なバランスを与えていることはあるでしょう。すべての人材が優秀であり完璧だなどという組織では、持続性がなかったり、どこかで突然破綻するようなこともあるかもしれません。その点、働かないアリの研究は、社会や組織に多様な人材を取り込むことで、ある意味でゆらぎをもたらし、持続性や永続性が達成できるのかもしれないということの示唆を与えてくれているようでもあります。



























