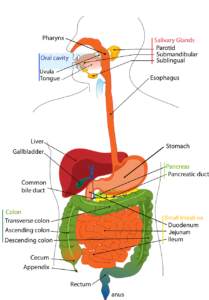ベストセラー書籍「ワクチンの境界」を定期的に無料公開しております。
前の記事はコチラ
この問題を考えるにあたって、本書では権力と倫理の関係から分析していきます。新型の感染症が発生し、様々な対策を打つのは国家(政府)の仕事です。対策を遂行するには権力が必要になります。そして、国民はその対策を受け入れるかどうかを判断することが求められます。倫理とは、このような外部からの要請を受けたときに、人間の判断に関わるものです。
もちろん、外部からの権力と内部からの倫理の方向性が結果的に一致することもあるでしょう。しかし、権力が特定の「倫理」を押しつけてくる場合には特に注意が必要です。なぜなら、そのような「倫理」は、「あなたのため」とか「社会のため」というように、簡単には否定できず、すぐに信じてしまいそうな言葉を伴って、人々の心の中に入ってくるからです。その結果、気がつくと自分自身の内面の深いところまで権力に侵入されていたということになりかねません。自分の内部に権力が侵入するということは、管理される領域が広がるということで、その分自由が制約されることになります。これは人間の自由という尊厳にかかわりますから、重大な問題です。
したがって、安易に人間の尊厳が毀損されないように、一人ひとりがしっかりと考えて、政府からの要請を受け入れるか、留保するか、拒否するか、あるいは意見を伝えるかを判断する必要があります。しかし、それを実行しにくい状況が生じているとすれば、それは政府の主張が正しいか、間違っているかに関係なく、危険な状態と言えます。なぜなら、社会が権力の主張を検証する手段を失っているからです。そうなると権力が間違ったときに誰も修正できず、その暴走を止められなくなります。
これは政府と国民の間にだけあてはまることではありません。すべての組織や人間関係において、簡単に誰かの要請に従うと、その要請が間違っていたときに大きな被害を受けますし、要請自体の内容を検証して改善する機会も失ってしまいます。このように考えれば、何らかの要請に従うか否かの判断の前に、その内容をよく調べて検証することが、一つの倫理的規範として成立しうると主張できます。
このことを体系的に主張したのが、19世紀の数学者で哲学者でもあったウィリアム・クリフォードです。その考えは、1877年に「信念の倫理」4 として発表されています。クリフォードの主張は、要約すれば「人間は軽々しく物事を信じてはいけない」ということに尽きます。しかも、その禁を犯せばその罪は何世紀にもわたって影響すると述べ、大変厳しい姿勢で議論を展開します。なぜ、クリフォードがここまで厳しく軽々しく物事を信じることを戒めたのか、その意味を問うことは、感染症対策に関する政府や専門家の説明に対する私たちの態度を批判的に見る目を与えてくれます。
一方、権力とは何でしょうか。近代社会の権力を理解するには、ミシェル・フーコーの権力論が有効です。フーコーの権力論のポイントは、近代の権力とは社会的な関係から生じる匿名のものであり、人間の身体や思考を規律する力であるとともに、生命や人口も管理する力(生権力)であるというものです。新型コロナウイルス感染症に対峙する権力は、まさにこの生権力そのものであると言えるでしょう。
もちろん、生権力が感染症対策に一定の効果を発揮していることは認めなければなりません。しかし、生権力は力ですから常に一定の方向へ向かって働きます。その行きつく先は人間の内面なので、それに対して何らかの抵抗をしなければ、人間は権力の操り人形になってしまうでしょう。フーコーはこの点について、「自己の自己への関係においてしか、政治的権力に対する抵抗点、第一にして究極の抵抗点はない」5 と指摘しています。この「自己の自己への関係」が倫理にほかなりません。
本書では、倫理を、社会的規範として記述された道徳と同義と見るのではなく、人間の生き方を規定する内面的な力にその本質があると考えます。それは力ですから、言語で表現することはできません。言語で表現された「倫理」は、単なる規則やコードにすぎず、本来の倫理ではありません。倫理は、そのような言語化された「規範」が形成される以前の主観の世界にしか存在しないものとして理解されるべきです。ルードウィヒ・ウィトゲンシュタインは、倫理を「人間の精神に潜む傾向」6 と説明しています。
そして、この傾向が複数の人間に共有されるとき、それは倫理として社会的に存在することになります。社会学者の宮台真司氏は、もう少し分かりやすく、倫理とは「許せないという感覚の共同主観性だ」7と述べています。その感覚がころころ変わってしまうと、複数の人間に共通する主観にはなりませんから、「『倫理のコア』は変えてはいけないとの強い貫徹意志があって初めて倫理になる」8と言えます。これをクリフォードの「信念の倫理」にあてはめれば、「調べないことは許せない」という主張になるでしょう。
権力はもちろん、倫理も力ですが、この二つの力は方向性が違います。権力は外部から人間の内面に働き、倫理は人間の内面から外部に働きます。しかし、権力が倫理と一体化してしまうと、権力が人間の内面から作用するようになります。これが、フーコーが明らかにした自己を自らが規律する権力です。権力が内面から人間を管理するようになると、人間は思考を停止し、指示に従う機械のようになってしまうでしょう。その典型が、ハンナ・アーレントが全体主義の本質であると批判した「凡庸な悪」です。
ナチスの迫害を受けた被害者でもあったアーレントは、全体主義の本質について最も深く考究した哲学者です。彼女は、ナチスドイツでユダヤ人虐殺を指揮したアドルフ・アイヒマンのイスラエルでの裁判を傍聴し、アイヒマンはユダヤ人を大量殺戮した極悪人ではなく、ただ思考を停止して指示に従っただけの凡庸な人間であることを指摘し、このような態度と行為こそが、全体主義の根源にあると主張しました9。それは、どこにでもあるありふれた、つまり人間の「凡庸さ」の中に潜む「悪」なのです。
新型コロナウイルス感染症対策が、国家の権力を利用して、国民を思考停止にして「凡庸な悪」を生み出しているとすれば、それは政策の是非に関わらず、重大な事態が進行していることを意味します。それを阻止するのは、人間の内面から生じる倫理の力しかありません。本書は、新型コロナウイルス感染症対策という事象を分析対象として、権力に対抗する倫理の役割を分析することを目的としています。これは二つの力の関係についての分析ですから、権力と倫理の力学と言ってもよいでしょう。
この分析枠組みは、新型コロナウイルスワクチンの問題だけにとどまらず、権力と倫理が対抗するあらゆる場面で適用できます。気候変動、原子力発電、ダイバーシティなど、現代社会には様々な難問が存在しています。しかし、社会は、それらが難問であるにもかかわらず、簡単に一つの答えを出して、それに向かって進もうとする傾向があります。そして、一旦進み出してしまうと、その方向が正しいか否かについての疑問までも封じ込めようとします。これはまさに全体主義的な傾向です。本書の分析枠組みは、このような全体主義的傾向をはらむあらゆる問題に適用できるものです。
本書は国家の権力を批判することを目的とするものではありません。感染症対策という緊急事態において、国家が権力を行使することは不可欠です。しかし、そこで国民が倫理的な視点を欠いてしまうと権力の暴走を簡単に止めることができなくなります。逆に言えば、国家による権力の行使を継続的に改善し続けるために、国民一人ひとりの倫理的な判断と行動が求められるのです。それは本来国家にとって、必要不可欠な要素のはずです。
なお、倫理的判断の結果、人々がどのような行動をとるべきかは、本書の考察の範囲の外です。本書は、ワクチンを含む感染症対策の是非に関しては、中立の立場から議論を展開します。なぜなら、国民一人ひとりが熟慮した結果として、感染症対策を支持しても、批判しても、あるいは判断を留保しても、そこに倫理的な視点が存在していれば、社会の分断が回避され次のステージが開かれるはずで、どのような判断に至るかは二次的な問題だからです。
しかし、感染症パンデミックという例外状態の下で、「自己の倫理の再構成が不可能であると感じさせるような何か」10 があるとすれば、それは社会の修復機能の不全を意味しますから、大きな問題であると考えます。その「何か」を克服して、自己の倫理を再構成するにはどうすればよいのか。これが本書が取り組むべき問題の核心です。
4 Clifford, W. E., The Ethics of Belief and Other Essays, Great Books in Philosophy, 1999.
5 フーコー「1982年2月17日の講義」(前掲)、294ページ。
6 ルードウィヒ・ウィトゲンシュタイン「倫理学講話」『ウィトゲンシュタイン全集第5巻』大修館書店、1976年、394ページ。
7 宮台真司「2020年パンデミックと「倫理のコア」」筑摩書房編集部編『コロナ後の世界―いま、この地点から考える』筑摩書房、2020年、71ページ。
8 宮台真司「前掲論文」、72ページ。
9 ハンナ・アーレント『イェルサレムのアイヒマン―悪の凡庸さについての報告』みすず書房、1994年。
10 フーコー「1982年2月17日の講義」(前掲)、294ページ。
ワクチンの境界 ― 権力と倫理の力学(國部克彦 著・アメージング出版)より