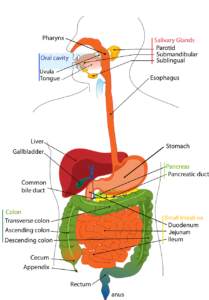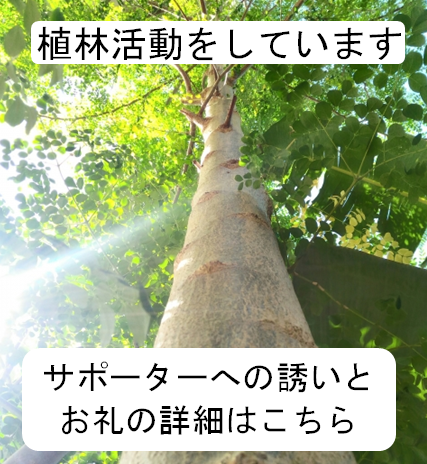暑い夏を乗り切るために、滋養強壮、栄養満点な沖縄料理をご紹介します。
沖縄の食文化の歴史
沖縄の食文化は琉球王国時代から日本本土や中国、東南アジアなどとの交流によって多様な影響を受けてきました。代表的な食材としては豚肉や海藻、島野菜などシンプルでヘルシーなものが多く、長寿の秘訣とも言われています。
また、沖縄の食文化は、戦後の米軍基地の影響でアメリカンスタイルの料理も取り入れましたが、伝統的な食材や調理法を大切に、温故知新の教えを今に引き継がれています。
沖縄の代表的な食材
代表的な沖縄食材をいくつかご紹介します。
・豚肉
アグー豚と呼ばれる豚は沖縄固有の貴重な豚として有名です。その歴史は古く、今から約600年前に中国から導入されたのがきっかけと言われており、一般的な豚肉よりも甘みと旨みがあるのが特徴です。
沖縄では耳(ミミガー)、足(豚足)、頭の皮(チラガー)など、鳴き声以外は全部食べると言われるほど、豚を愛食されています。疲労物質の乳酸が体に溜まるのを防ぐビタミンB1を多量に含み、鉄やリンなどのミネラル、コラーゲンも含みます。
・ゴーヤー
ゴーヤーの原産地はインド東北部で、中国には14世紀末頃に伝わり、日本へは中国経由で慶長年間(1596~1615)に渡来したと言われていますが、沖縄には本土よりも早く15世紀の前半までには伝わっていると考えられています。
特徴的なのはビタミンCが豊富なことで、その量はレモンの約1.5倍で、加熱しても壊れにくいそうです。
また、特徴的な苦みであるモモルデシンという成分は、肝臓に優しく、胃腸を刺激して食欲増進に効果があると言われています。
苦味が苦手な場合は塩もみした後、水気を切ると苦味が和らぎます。
・島ニンジン
17世紀にシルクロード、中国を経て日本に伝わり、黄色が特徴の沖縄の在来種です。
島ニンジンにはカロテンが豊富に含まれており、カロテンは「活性酸素」の発生を抑えたり除去したりする作用のある「抗酸化物質」として、動脈硬化や細胞の老化などを予防することに役立ち、また、油と一緒に調理すると吸収がよくなります。
もずく
古くから全国各地で食用にされてきた海藻の仲間であり、沖縄地方では昔よりもずくを三杯酢で食されていた為、酢のり=「スヌイ」とも呼ばれております。
このもずく類は多くの種類があり、その中で主に食用とされているのは6種類で国内で産業的規模の養殖は沖縄だけが成功し、全国で食べられているもずくの99%は沖縄県産です。
もずくは食物繊維やミネラルを多く含んだ低カロリーのヘルシー食品です。
さらに食用のみならず、ヌルヌル成分に含まれているフコイダンは、健康食品や化粧品、医療品等への産業利用が期待されています。
沖縄食材を使った料理例
栄養たっぷりの沖縄食材ですが、代表的な料理をいくつか紹介します。
・ゴーヤーチャンプルー
ゴーヤーを縦半分に切り、種とワタをスプーンで取ります。
豆腐を食べやすいサイズに切り、ランチョンミート(豚バラでも可能)を短冊に切り、白ダシなどお好みの調味料を加え炒めます。
豆腐に焼き色が付けば溶き卵を絡め炒めます。
ゴーヤーを麩(車麩、焼き麩)に変えればフーチャンプルーです。
チャンプルーとは沖縄の方言で「ごちゃ混ぜ」の意味となります。
・ラフテー
沖縄風豚の角煮です。
皮付き豚のブロック肉を1時間程度下茹でした後、醬油、みりん、砂糖を混ぜ合わした調味料で1時間程度煮ます。ブロック肉単体でも美味しいですが、香味野菜としてネギやショウガと煮れば更に美味しいです。
時間はかかりますが、しっかり煮込めば飴色でプルプルとした食感のラフテーとなり、そのまま食べても沖縄そばに入れて食べるのもおススメです。
・人参しりしり
島ニンジンがいいですが、手に入らない場合は西洋にんじんでも大丈夫です。
ニンジンの皮を剥き、薄切りまたは細切りにします。
ピーラーを使ってもいいですし、人参しりしり専用の摺木もあり時短に効果的です。
切った人参を油で炒め、柔らかくなってくればツナ缶を油ごと入れて炒めます。味付けはシンプルに塩コショウだけでもいいですが、お好みで白ダシや中華スープの素に変えても美味しいです。
ある程度炒めたら、溶き卵を絡め炒めます。
まとめ
沖縄の食文化、食材、料理をご紹介しましたがいかがだったでしょうか?
沖縄の歴史と文化に触れながら滋養強壮、栄養満点の沖縄料理を食べ、この暑い夏を乗り切りましょう。
参考文献:琉球料理のきほん